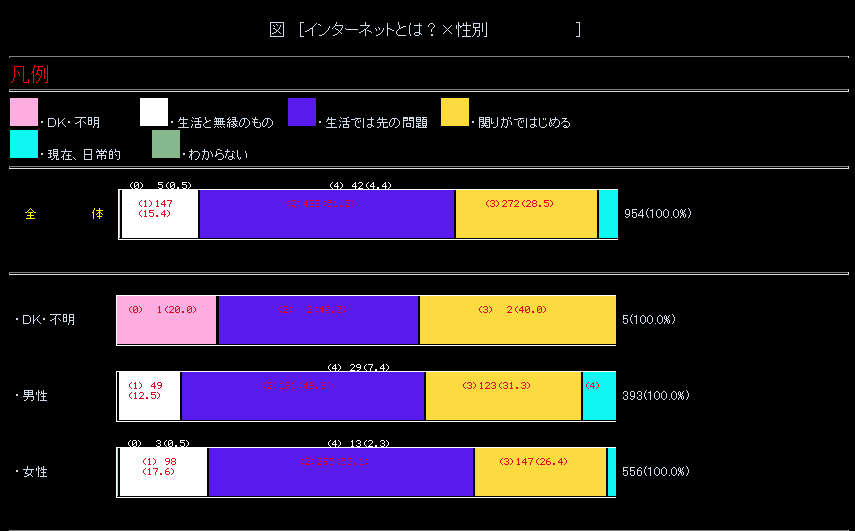学内WWWあんなページこんなページ 第2回
教育学部附属大学教育開放センター
教育学部附属大学教育開放センター 似内 寛
nita@kai-c2.kai-c.tohoku.ac.jp
大学教育開放センターは昭和48年の設立より,約四半世紀にわたり
一般市民を対象とした「東北大学大学教育開放講座」を行っております。
センターの規模は大きくありません(現員:教授1名,助手1名)が,
東北各地の放送局と協力して実施している東北地区「大学放送公開講座」
などにより,県内ばかりでなく,東北各県の地域住民からも親しまれています。
このようなセンターの活動にとって,
これまでの最大の隘路が,みずから十分な広報手段を持ち得ないということでした。
地域社会にむけられた大学の窓口としての本センターにとって,
インターネットの活用は,広報手段としてばかりでなく,
21世紀の「大学開放」のあり方を考えるとき,不可避の方向ですし,
わが国の国民的課題である生涯学習を地域社会で推進していくうえでも,
“切り札”になると考えて,積極的にとりくんでおります。
1 ページ作成
本センターが実験的にWWWサーバーを立ち上げたのが,1995年の秋のこと
(Windows NTで,無料の[HTTP Server(EMWAC)])でした。
学部2年(教育学部教育社会学専攻)の基礎演習の時間でのことです。
それから半年ほど,準備と機材整備と勉強にあてました。
この間,Javaが登場し,WEB上で学生たちの顔写真を回転させたり,
流したりするのに成功して,みんなで歓声をあげたこともありました。
本センターのWWWサーバーの公開をはじめたのは,次の年度になってからです。
FDDIに接続したサンのワークステーションに,[NCSA HTTPd]を立ち上げました。
これが,現在の本センターのホームページを発信しています。
現在のホームページのデザインは,学部学生が作成したいくつかの
原案から最終案を選定し,それに手を加えて作成しました。
また,そのなかに,``Java掲示板''という簡単なJavaアプレットも組み込みました。
本センターでは,これまで開放講座用の印刷物をつくる
DTP用プログラムや種々の地域調査のための集計プログラムを作成してきましたので,
インターネットの最近の技法であるCGIやJava言語についてもなんとかやれておれます。
2 ページの内容
ホームページの構成は表紙のページをフレームで三つに区切り,
上部の一つには講座のイメージが入れ替わって表示されるJava
アプレットと「大学教育開放センター」の文字を表示し,
その下の左のフレームにメニューを,右のフレームにメニューでクリックされた
内容を表示するようにしました。メニューは「開放講座案内」「研究開発計画」
「L&M研究会」「研究開発チーム」「センターの紹介」の5つに分かれています。

図 1: 大学教育開放センター表紙ページ
このうちの「研究開発計画」は,
大学が地域社会や全世界に向けて情報を提供することに
「大学開放」の機関として本センターがどのように貢献できるのかを
考えていくためのものです。
また「L&M研究会」は「東北地区生涯学習とマルチメディア研究会」の略称で,
本センターが, 平成6,7年度に開催した開放講座「生涯学習指導者養成講座」に
参加した東北各県市町村の教育委員会にはたらきかけて,
「東北地区における生涯学習のあり方を,とくに最近のマルチメディア時代への動きと
かかわらせて探究し,もって東北における生涯学習の振興とその新しい展開をめざす」
ことを目的に組織した研究会です。
「センターの紹介」には本センターが25年間に行ってきた各種講座や,
研究集会の記録と,研究ノート『大学と社会』の一覧を掲載しています。
これらの記録はさらに今後詳細なものにしていく予定です。
また,生涯学習とマルチメディアに関して,本センターが東北各県の
400市町村を対象にして平成6年度より毎年行っている
「地域生涯学習計画」調査シリーズや,平成9年に行った「仙台市民意識調査」,
並びに秋田県湯沢市での調査「湯沢市民意識調査」の結果も公開しております。
これらの調査は将来インターネットなどのマルチメディアとネットワークの技術が
もっと一般的なものになったときに,それを生涯学習活動に応用する方法を
考えるための調査です。
調査結果の公表については試験的な試みとして,クロス集計を
WEBページ上で行えるようにしております(CGIプログラムで,
gif imageの出力にあたっては,[gd gif-manipulating library, version 1.2.]
を使用しております。)。
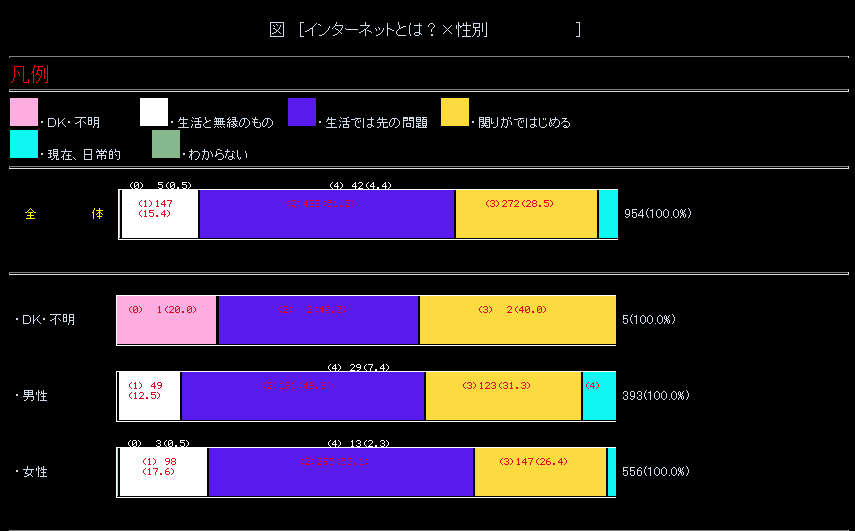
図 2: クロス集計グラフ出力
3 今後の方針
インターネットの活用は大学教育の開放にとって,
新しい形を作り出す可能性を持っています。
それは例えば地理的に離れた地域の方々が大学にアクセスし,
オンラインで自分の学習に役立つ情報を手に入れたり,
また開放講座の講義の補足情報や参考文献情報を掲載し,
そのページを中心に講座の受講生の学習サークルの場として,
距離や時間に縛られずにディスカッションをする,
あるいは自治体の生涯学習担当者が地域生涯学習の企画・運営に関する問題を
解決するための情報センターとして機能することなど,いろいろな可能性があります。
本センターではWEBをはじめとしたネットワーク技術の利用に,
本格的に取り組む必要性があると考えております。
本センターでは,こうしたことを積極的にすすめるために,現在,
秋田県湯沢市をフィールドに,地元の市民のみなさんの協力もあおぎつつ,
“仮想生涯学習センター”の構築をすすめています。
これは,また,教育学部の教育社会学・社会教育学講座の3年次学生の
社会学実習の授業の一環としてもすすめられています。
このなかでは,Javaで作成した,「地域ニュース提供システム」
「生涯学習情報コーナー」「湯沢市仮想商店街」「湯沢市仮想物産館」などが
動いています。
まだ,実験段階(現在,日本語に対応させるために,マイクロソフトの[J++]で,
コンパイルしたものを公開しています。
また,Javaの最新版[JDK1.1.2]の国際化バージョンで,
日本語対応プログラムも動きはじめておりますが,
これに対応するブラウザとしては,[Hotjava1.0][1997年6月30日現在]
しかありませんので,ご了承ください。)の試みですが,
学内のネットワーク環境では,それほどいらいらせずにご覧になれると思いますので,
時間のあるときにはのぞいてみてください。
www-admin@tohoku.ac.jp
pub-com@tohoku.ac.jp