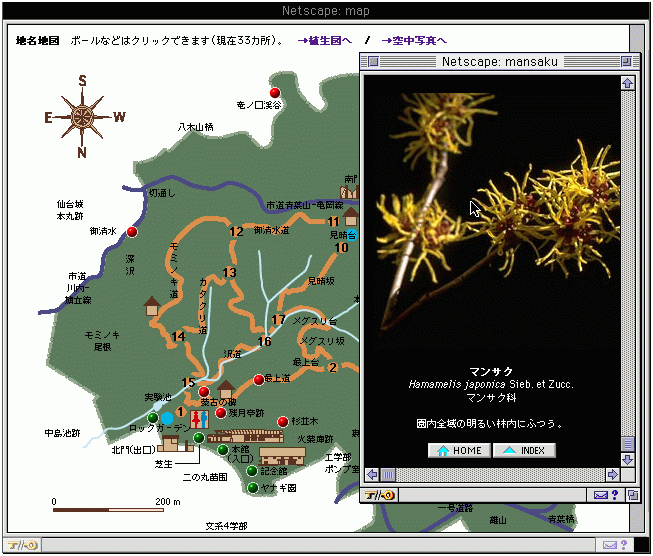学内WWWあんなページこんなページ 第4回
東北大学理学部附属植物園ホームページ
理学部附属植物園 平塚 明
hiratsuk@biology.tohoku.ac.jp
1 植物園は,市民に開かれた施設です
ですからそのホームページも,園内地図や開園期間・料金等の利用案内,
植物・動物や史跡の紹介などから構成し,写真や図を多用しています。
96年に新築された本館のリアル展示(実物・模型・パネルを使った展示)を
つくるときから,オンライン展示(展示室内のモニターに表示する,ある
いはネットに載せて外部からも見られる展示)を含めることを構想してい
ました。図表の多くは初めからコンピューターでつくり,出力センターで
パネル化したものをリアル展示に使いました。97年にホームページをつく
ることになった時も,この蓄積がそのまま使えるものと思っていました。
しかし実際には,大きなパネルで展示する場合と,狭くて解像度も限られ
るモニターで展示する場合とでは,図や画像の作り方を変えないといけな
いことに気づきました。ほとんどすべての素材は改めてつくりなおしました。

図 1: 植物園ホームページのトップページ
2 展示にあたっては次のような原則を立てました
オリジナルなデータ・文章を使う…当然のことですが,手間のかかること
でもあります。例えば展示に用いるために,改めて園内の植生調査を行いました。
こどもにもわかるように表現するが,内容のレベルは落とさない…各分野
の専門家・研究者に御協力いただきました。専門の論文の中の図は,描き
直しました。学問的な意義が大きくても,わかりやすく表現するのが難し
く,ボツにしたものもあります。文章の校正は,卒業生で新聞記者をして
いる方に依頼していますが,コンテンツの更新が激しいので,追いつきません。
植物園領域の「総合的」な解説をめざす…植物,動物,地質の理科的な面
はもちろん,そこでなされた人の営為,人文歴史についても言及しました。
しかし,足りない所は沢山あります。あくまでも,植物園とその周囲の具
体的な事例を解説しながら,普遍的な事実に言及するようにしました。
良質の図・写真を使う…例えば印刷物としての地図をスキャンして取り込
むようなことはせずに,ディジタル版の地図をつくることから始めました。
取り込みによる画質の低下・字のかすれが気になるからです。写真は園内
外の名手から提供してもらいました。銀塩フイルムで撮影したものを
PhotoCD化,あるいはフイルムスキャナーで取り込みました。ディジタルカ
メラの進歩も著しいのですが,銀塩粒子に優るとは思えません。もちろん,
画質がわるくてもかまわない対象,速報性が求められる素材については
ディジタルカメラも用いています。
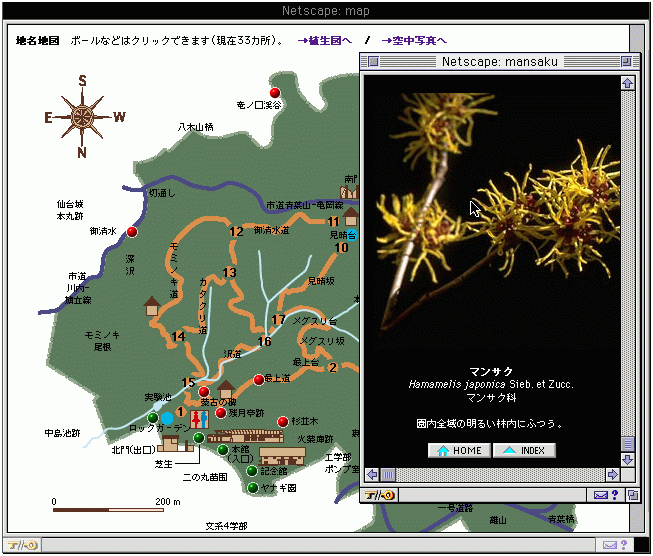
図 2: 園内地図のクリックから,そこに生育する植物の画像ウインドウへ
3 アクセスしてほしいと仮定した人(お客さん)は
a: 植物園に行きたくても行けない人,b: 花や園芸の好きな人,c: 小中
高校の先生及び生徒,などです。aにはなんらかの理由で動けない人,ある
いは雨(雪)の日のナチュラリストも含まれます。bに属する人は昨今のブー
ムから数は多いと思うのですが,実際に園を訪れる方はわずかです。東北大
植物園には高山植物を植えたロックガーデンもありますが,基本的には自然
林をそのまま見せている所であり,印象は地味です。しかし見るべきものは
多く,そこを紹介し解説するのが,ホームページを含めた展示の務めです。
理想はガイド(人)による案内ですが,これは今後の課題です。cでは,とく
に先生方に期待しています。先生がホームページをみた上で,生徒達を実際
に連れてきてくれたら入園料収入も多少は上るだろうとの虫のいいことを考
えています。なお,他大学の教官(植物生態学専攻)で,当ホームページを授
業の教材として使って下さっている方がいます。
上に述べた人たちと,Webを自由に閲覧できる層とがどれぐらい重なるかは
わかりません。開設当初は大学関係者のアクセス数が多かったのですが,主
な検索エンジンに登録されてからは,その他の方も大勢訪れてくれます。
4 Webページとして,難しいテクニックは何も使っていません
リンクとクリッカブルマップこそが真髄だと思い,積み重ねと頻繁な更新
をモットーとしています。たとえアマチュアでも時間をかければデザイン
も技術も優れたものができる,あるいはアマチュアだからこそ時間がかけ
られると思います。しかし斬新な表現や技術でも,その風化は早い上に,
本質的な内容から却って目をそらせてしまいがちです。同じ時間を使うな
ら信頼できるデータの蓄積に回した方がよいと判断しています。力の配分
としては技術を含めたデザインに3,データ収集に7といった割合でしょう
か。ホームページを作っている方はどなたも同じでしょうが,ファイルサ
イズと画質の妥協点(減色・加工・圧縮)を探るのに時間がかかります。季
節の話題を随時折り込んで,私たちを囲む植物たちとのつながりが意識で
きるようにしたいと思っています。
5 …とはいえ
今後の改良点としてはまず表現技術を高めることです。やはり見てもらわ
なければ仕方がありません。植物園ホームページの競合者は大学や研究所
ではありません。他の文化施設や行楽施設,観光地など「休日」に人が集
まるような所は皆ライバルです。その中で目立つには洗練されたデザイン
やテクニックが必要です。その点,現在のページは素っ気ない仕様書のよ
うなものです。これを元にして,Webデザイナーに華のあるものをつくって
もらえたらと思います。もちろんそれは不可能であり,素人なりのよさも
あると勝手に思うしかありません。(それにしても,最大の失敗はホームペ
ージのタイトルでした。「東北大学理学部附属植物園ホームページ」。長
い。漢字が多い。固苦しい。これではなかなか人が寄りつきません。組織
としての正式名と,ホームページとしての名前は別でも構わないことに早
く気づくべきでした。)
専門研究者にとっては,植物園の保有する種(しゅ)のリストが重要です。
このデータベース部分が弱く,現在はダウンロードしたリストをブラウザ
側の機能で検索してもらうような原始的な代物です。天然記念物の自然林
構成種や,世界から収集した貴重なヤナギ科植物のコレクションがあるの
で,早急に整えなければならないと思っています。
6 今のところ双方向性は意識していませんが
時折,生き物についての質問が飛び込んできます。一般的と思えるものに
ついては,コンテンツに反映させています。オンライン展示には欠点も沢
山ありますが,リアル展示では不可能な枚挙的データの展示ができること,
落ち着いて見てもらえること,低コストであることに加え,広域性と速報
性・即応性は強力です。作り手の構築法・継続の意志にもよりますが,リ
アルタイムで発信したものが霧のように消えていくのではなく,常にコン
テンツに蓄積し,そこに誰でもがアクセスできるという機能は,他のメデ
ィアにはできないことでしょう。
7 ホームページで満足してしまって,実際に入園者は来ないのではないか…
との古典的な危惧はもっていません。植物園に来ない人は,ホームページ
を見ても見なくても,やはり来ないからです。さらに言えば,リアル植物
園とネット上の植物園はある程度独立した存在だと感じるようになりまし
た。リアル植物園には足を運ばないが,植物や自然には大いに関心があり,
ホームページを頻繁に訪れるというような方は沢山います。そうした方に
も満足していただけるようなページ作りをしたいと思います。ただ,ホー
ムページではすべてを語らずに,例えばなんらかの予備知識を示した後に
設問をし,それを解きに足を運んでもらうというようなことは考えられま
す。また,所属スタッフの研究内容も,もっと載せていくべきでしょう。
植物園ホームページは,ただの電子パンフレットではなく,オンラインで
の展示・イベント・サービス・データベース・出版・研究発表を含んだ
「もう一つの植物園」として,博物館活動の中に位置づけていくべきもの
だと思います。
8 国際政治に環境カードが使われる時代です
植物園も従来の「守り」から,少々「攻め」るぐらいの気持ちに切り替え
ないと,自分たちの森をたもつことさえ不可能になってきました。最大の
武器は正確で豊富な知識であり,それを市民に提供するのがホームページ
を含めた展示の役割でしょう。(そんな固いことを言わなくても,美しい花
の写真を眺めてもらうだけでも充分なのですが。)
www-admin@tohoku.ac.jp
pub-com@tohoku.ac.jp